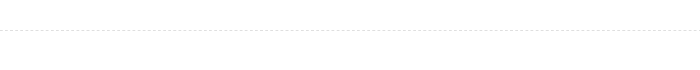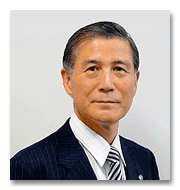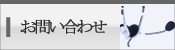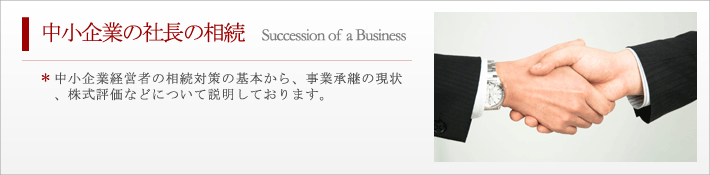中小企業の社長の相続
a-16. 遺言の効果とその注意点
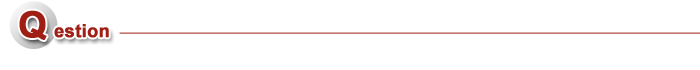
友人から「会社継続のためには遺言書を書いておいたほうがいいよ。」と言われました。遺言書はどういう場合に必要ですか?
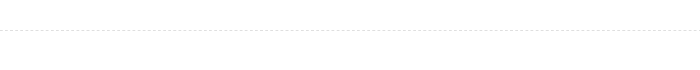
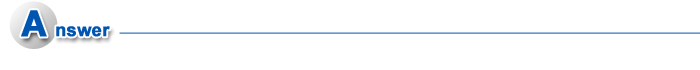
- ① 会社や事業を特定の人に継がせたい場合
- 後継者に遺言で事業承継をさせないと、会社や事業の資産が相続により分割されてしまい、会社や事業の存続が不可能になってしまいます。特に、事業承継の場合は事業後継者に遺言で株式を相続させることが不可欠です。
- ② 法定相続人に遺産をあげたくない場合
- 例えば、長男は一生懸命に親と共に事業に専念しているが、次男は浪費癖があり、さんざん親不孝を重ねているような場合に、長男に会社の株式を全部相続させようと思っても遺言なしに相続となると、次男も株式を相続することになります。(ただし、次男には遺留分があります。)
- ③ 遺留分に注意して、遺産を特定する分割方法が良い
- 遺留分を侵すと、後日相続人から「遺留分の減殺請求」がある場合もあります。その準備として、後継者以外には株式の一部を無議決権株式とした上で遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成しておくとよい。
- ④ 遺留分の減殺請求権とは
- イ.「遺留分」とは、妻や子供、直系尊属は遺言書の内容に関わらず、一定の範囲で最低限の相続分が保証される制度です。遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害した人に対して、「遺留分減殺請求」、すなわち遺留分に相当する財産を渡せという請求が出来ます。
- ロ.この請求は、相手方に対して書面で行います。重要な書面ですから、配達証明付きの内容証明郵便で行います。
- ⑤ 遺留分をどうするか
- イ.遺留分権利者が遺言に不服であっても、相続開始の後一定期間内に取戻を主張しないと権利は時効で消滅します。
- ロ.遺留分についての争いは裁判所で解決してもらえます。その場合、遺留分権利者に一部の遺産を返還することになるかもしれませんが、金銭があれば金銭で賠償すればよく、会社の株式や事業用不動産等の現物を返還する必要はありません。
- ハ.また争いを未然に防ぐために、あらかじめ遺言の中で遺留分権利者に遺留分相当額の金銭を何らかの形で、例えば受取った生命保険金で支払うように決めておくこともできます。