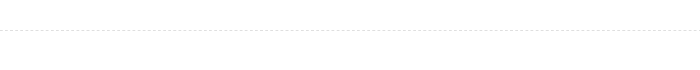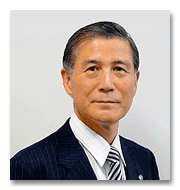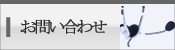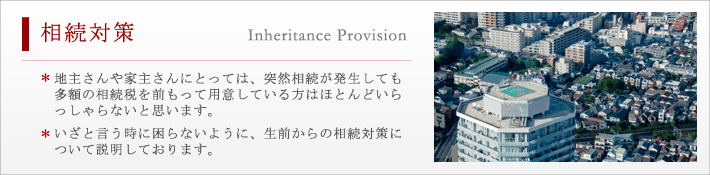相続を争続にしない方法等
c-11. 遺留分の放棄とは
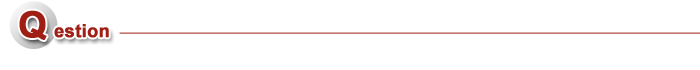
私の次男の会社が倒産し、保証人だった私が借金を返済しました。その代わりに「遺産は一切もらわない、放棄する」という念書を書かせましたが大丈夫でしょうか。
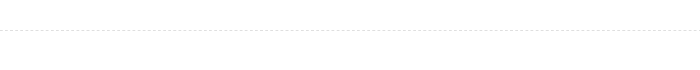
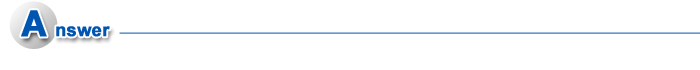
- ① 生前に相続放棄をしても無効
- 相続は人の死亡によって開始されるので、生前に「相続を放棄する」旨の念書を書かせても無効です。しかし、被相続人の生きている間に相続人が家庭裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」をすることは認められています。
- ② 遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要
- イ.「遺産は一切もらわない、放棄する」という念書があっても、何の法的効果も生じません。例えば、次男が一切相続しないということを確実にするには、遺言で次男には何も相続させないということを明記し、かつ次男が遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てないといけません。
ロ.遺留分の放棄の申し立てがなされると、家庭裁判所で審査が行われます。誰かに強制されていないか、放棄したいと考えた理由は何かが審査され、問題がないと判断されたときに許可されます。許可がなされて初めて遺留分の放棄が認められるのです。 - ③ 許可申し立てをする動機
- イ.生前に多額の贈与を受けていること。
ロ.非嫡出子の認知を受ける条件として。
ハ.一次相続では遺産を取得するが、二次相続では放棄するため。
(名古屋弁護士会法律研究部編集「遺留分の実務」より) - ④ 許可の要件は、放棄を強要されることなく、あくまでも本人の自由意思に基づき相当な理由があること。