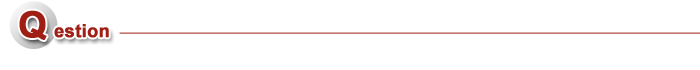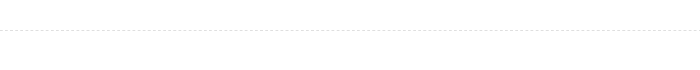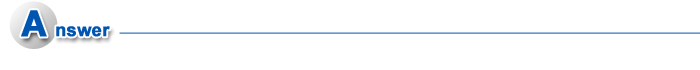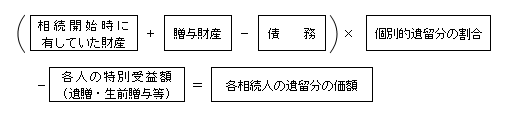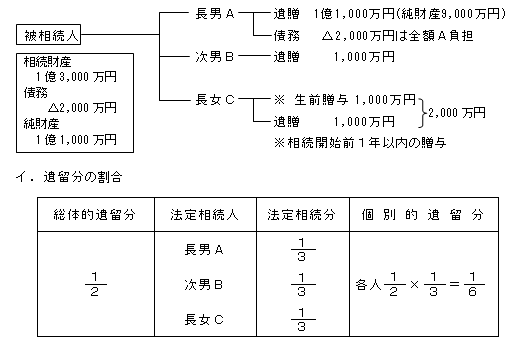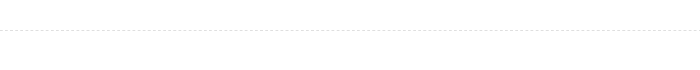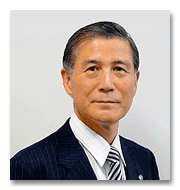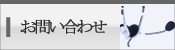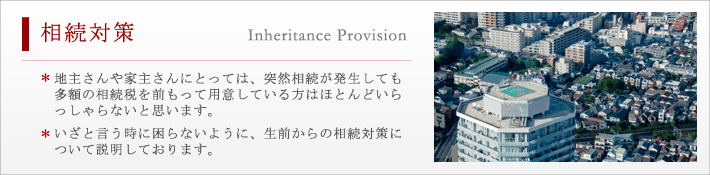|
|
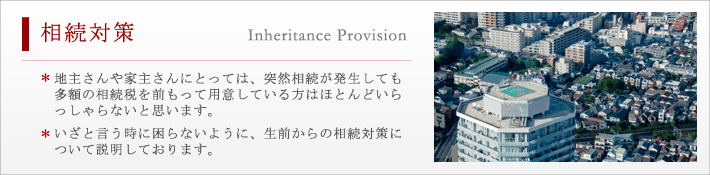 |
|
相続を争続にしない方法等
c-08. 遺留分の意義とその計算
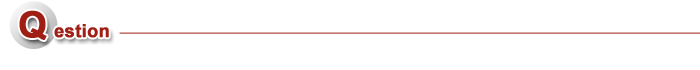
私は、長男に財産を多く相続させるように公正証書遺言を作ってありますが、相続開始後、他の相続人との間でどう遺留分が問題になるのでしょうか。
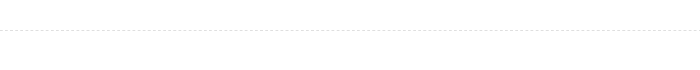 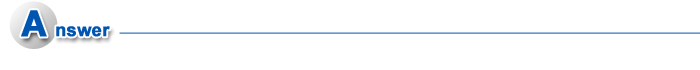
- ① 遺留分の意義
- イ.前に述べたように、遺言は原則として自由です。従って、妻と子供3人がいても「妻に全財産を相続させる」という遺言も自由に出来ます。しかし、場合によって、何の相続も出来なくなった子供が生活に窮することもあります。そこで民法は、配偶者・子・直系尊属には、遺言の内容に関わらず、一定の割合の相続権を認めることにしています。これが、「遺留分」です。
ロ.遺留分は、遺留分を侵害された人が権利を主張して初めて効力を生じます。先の例で、子供3人はそれぞれ遺留分をもっていますが、それを主張しなければ、遺言どおりの相続がなされることになります。
- ② 遺留分権利者
- イ.遺留分が保障される法定相続人を「遺留分権利者」といいます。
ロ.遺留分権利者は、被相続人の法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者、すなわち、配偶者、子や子孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属です。
ハ.相続人全体の遺留分の割合(総体的遺留分)は次の通りです。
1.配偶者、直系卑属が相続人であるとき ── 被相続人の財産の1/2
2.直系尊属のみが相続人であるとき ──── 被相続人の財産の1/3
- ③ 遺留分の算定
- イ.遺留分の額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価格に、相続開始前の1年間に贈与したことがある場合にその贈与の価格を加え、そこから債務全額を引いて計算することと定められています。
ロ.上記イで算定した価額を基礎として各相続人の遺留分が計算されます。これを算式で示すと以下のようになります。
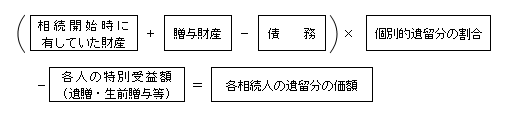 - ④ 遺留分算定の基礎となる財産の範囲
- イ.相続開始の時に有した財産、遺贈の目的とされた財産もこれに含まれます。また、死因贈与された財産も遺贈財産として扱われます。
ロ.一定の贈与財産
1.相続開始前1年以内にした贈与
2.1年前にした贈与のうち贈与者、受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与財産
3.みなし贈与財産
低額譲渡益、債務の免除・弁済益等。負担付贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したもの。これらのみなし贈与財産については、1年以内に行われたものに限りません。
4.相続人が、被相続人から婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として受けた贈与
(東京弁護士会法友全期会相続実務研究会編「遺産分割実務マニュアル」より)
- ⑤ 具体的計算例
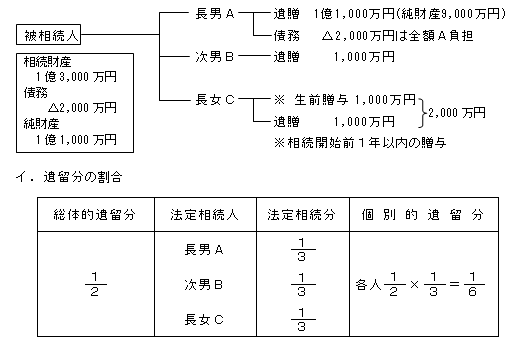 - ロ.遺留分の計算
相続財産 長女Cの生前贈与分 債務
次男B(13,000万円+1,000万円-2,000万円)× 1/6- 1,000万円=1,000万円
長女C(13,000万円+1,000万円-2,000万円)× 1/6-(1,000万円+1,000万円)=0
- ハ.上記ロより次男Bは、長男Aに対し1,000万円の遺留分減殺請求権を有することになります。長女Cについては生前贈与、遺贈財産の価額の合計が遺留分の額に等しいため、長女Cの遺留分は存在しないことになります。
- ⑥ 相続人の1人が遺留分を放棄した場合
- イ.共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分には影響がありません。
ロ.相続人が息子3人のとき、長男に全財産を譲る遺言をして、次男は遺留分を放棄したが、三男は放棄しなかった場合、三男の遺留分1/6(1/3×1/2)に変わりはありません。
- ⑦ 遺留分の減殺請求権
- 遺留分を認められている相続人(配偶者・子・直系尊属)は、遺留分を侵害された場合、遺留分の範囲内で遺産を取り戻すことができます。この権利を「遺留分減殺請求権」といいます。この権利は相続の開始および遺留分の侵害があったことを知った日から1年間行使しないと時効で消滅します。
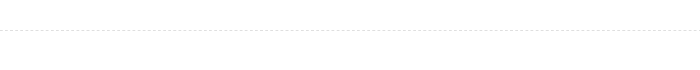
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|