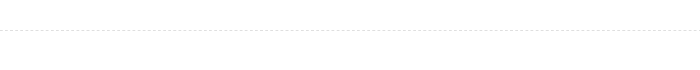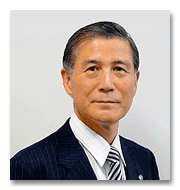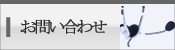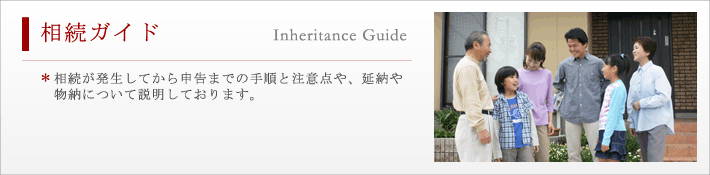相続発生後の準備
a-3. 申告に必要な書類と業務の手順
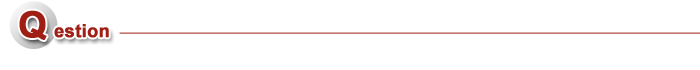
相続税の申告をするにつき、どのような書類が必要なのでしょうか?
必要書類の集め方や申告業務について教えて下さい。
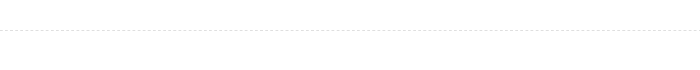
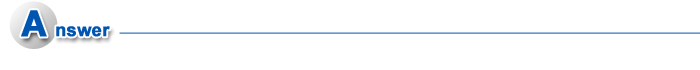
- ① まず最初に相続人の確定を
- イ. 相続人の確定を間違えたら、すべてがパーになります。
- ロ. 相続人を戸籍謄本・抄本・住民票等で確認します。
- ② 財産評価に必要な書類の収集
- イ. 土地建物等の評価、その他の財産の評価、預貯金の残高の確認をします。
- ロ. マイナス財産としての借入金や未払税金等の債務、葬式費用を把握します。
- ③ 金融機関の数だけ余分に必要な書類あり
- イ. 不動産の相続登記と金融機関の預貯金の名義変更に必要なものがあります。
- ロ. その分別途に(A)分割協議書、(B)印鑑証明書、(C)戸籍謄本・抄本を用意します。
- ④ 戸籍の関係書類は司法書士等の専門家に依頼した方がよい
- イ. 養子縁組している場合や相続人が多い場合には相続人が洩れる場合があります。
- ロ. 被相続人が長生きし、その前に実子が亡くなっている場合には代襲相続人が相続人の地位を引き継ぎます。
- ⑤ 不動産の登記簿謄本、公図、建物図面も同じ
- 固定資産税評価証明書と謄本との所有者、地目、面積等の照合や抹消されていない権利関係の有無を確認します。
- ⑥ 遺言書の有無の確認
- 自筆証書遺言が発見されれば、その保管者は民法第1004条の規定により、遅滞なくこれを裁判所に提出してその検認を受けなければなりません。
- ⑦ 相続税の税務調査の実態を知っておく
- 無事に申告が終ったと安心していても、後日税務調査で多額の申告漏れを指摘されない様に税務調査の実態を知っておく必要があります。
- ⑧ 申告に必要な書類の収集
- ※ 納税猶予の適用を受ける農地相続の場合は、別途書類あり。
- ⑨ 申告業務の進め方
- イ. 民法上の相続人と相続税法上の法定相続人の数の確定
- ロ. 土地建物の利用状況と建物の未登記物件の現状確認
- ハ. 土地の測量図または地積図と現況との比較検討
- ニ. 四角い整形地の簡易測量と測量図の作成、混合地は測量士に依頼
- ホ. 同一の利用目的の土地一区画ごとの評価計算明細書の作成
- ヘ. 構築物その他の財産の確認と評価計算明細書の作成
- ト. 預金の過去3年間の移動状況の確認と定期預金の利息計算
- チ. 借入金、未払金、預り敷金、保証金および葬式費用の内訳書作成
- リ. 相続財産の明細書の作成と相続税額の計算
- ヌ. 全相続財産を相続人へ提示し、分割協議の開始(遺言の有無の確認)
- ル. 遺産分割協議書に各人が自署し実印押印、印鑑証明書添付
- ヲ. 相続財産の相続登記と預貯金の名義変更手続き
- ワ. 相続税申告書および附属明細書に各人が実印押印(認印でも可)
- カ. 延納の場合は延納申請書、抵当権設定承諾書、担保提供書に押印
- ヨ. 物納の場合は物納物件の測量図、案内図、申請書等の提出
- タ. 担保財産の財務省職権による抵当権設定登記の完了
- レ. 物納の収納許可
- ※ 納税猶予の適用を受ける農地相続の場合は、別途手続きあり。
| No. | 必要書類 | 申請場所 | 必要枚数 |
|---|---|---|---|
| 1. | ①被相続人の除籍謄本 ②原戸籍謄本 ③戸籍の附票 | 区役所または市町村 | 各4通以上 |
| 2. | 死亡診断書 | 病 院 | 1通 |
| 3. | 相続人の戸籍謄本、婚姻により除籍した人は戸籍抄本 | 区役所または市町村 | 各4通以上 |
| 4. | 被相続人の除票・相続人の住民票 | 出張所または市区町村 | 各2通 |
| 5. | 被相続人の略歴書(出身地、最終学歴、職業・役職等、住所の移転状況、病歴、入退院の経過) | ||
| 6. | 相続人の現況経歴書(住所、氏名、勤務先、生年月日、電話番号) |
||
| 7. | 土地建物の死亡年度分の固定資産税評価証明書 (道路の非課税も含む) |
納付書持参の上 ・・・都県税事務所または市町村 |
各2通 |
| 8. | 土地建物の登記簿謄本 | 評価証明書の地番と家屋番号で申請 ・・・登記所 |
各1通 |
| 9. | 土地(借地等についても)の公図 | 登記所 | |
| 10. | 土地の測量図、特定事業用宅地または特定居住用宅地に該当の有無とその地積 (不整形地、建物が複数建っている土地、売却予定地は正式な測量図) |
||
| 11. | 建物の配置図 (全体の土地の利用状況の説明可能なもの) |
||
| 12. | 建物の建築確認書(あるものだけでも)、建物図面(権利証にセットしてあり) | 登記所 | |
| 13. | 貸地、貸家の賃貸借契約書 (ない場合は賃借人の住所、氏名、契約期間の一覧表) |
||
| 14. | 生産緑地の指定を受けた農地の明細書 | 農業委員会・都市計画課 | |
| 15. | 死亡年度分の固定資産税納付書、課税明細書又は名寄帳 (納税証明書でもよい) |
都県税事務所または市役所 | |
| 16. | 個人の確定申告書の過去2年間分、当年の準確定申告書 (死亡後4ヶ月以内提出) |
||
| 17. | 同族会社の株主は、株式評価に必要な決算書および所有資産の評価計算明細書 (取引相場のない株式の評価方法の改正に注意) |
||
| 18. | 金銭信託、貸付信託、公社債、株式、その他の有価証券がある場合は、その証券、預かり証、銘柄の明細書 | 証券会社 | |
| 19. | 被相続人の過去3年間の預金通帳 (ない場合は金融機関から元帳をもらう) |
||
| 20. | 死亡日現在の預金の残高証明書、出資金の残高証明書、定期証書の写し (残高のある金融機関はすべて必要) |
金融機関 | |
| 21. | 被相続人のものでありながら借名預金や相続人名義になっている預貯金の確認 (贈与税の申告をしていない分) |
||
| 22. | 親類、子供に対する事業資金等の貸付金の有無、贈与税の立替負担の有無 (預金の大口支払先・他の相続人より確認) |
||
| 23. | 親類、知人の会社の株主である場合は株主名簿 (株主でない場合は必要なし) |
株主になっている会社 | |
| 24. | 車両、機械、器具、家庭用財産のうち10万円を超えるものの明細書 (購入年月日、価額、名称等) |
||
| 25. | 積立火災保険を死亡日現在解約したと仮定した場合の解約返戻金明細書 (前納の火災保険の解約返戻金に注意) |
保険会社 | |
| 26. | 生命保険金の支払明細書、退職金の支払明細書と受取人の確認 (確定申告で控除済のものはまずあるものとして) |
保険会社・勤務先 | |
| 27. | 相続開始前3年以内に相続人等が贈与を受けている場合はその内容 (預金証書又は通帳からの引出し記録の確認) |
||
| 28. | 葬式費用(お通夜と告別式当日の費用)の領収証 (初7日から先の法事の支払は該当しない) |
||
| 29. | 公祖公課の未払いの有無 (所得税、住民税、固定資産税等) |
||
| 30. | 債務(借入金)がある場合は、その明細と使途・預り敷金及び保証金の明細書 (残高証明書・賃貸借契約書) |
金融機関 | |
| 31. | 相続人全員の印鑑証明書 (分割協議書・抵当権設定承諾書に使用する) |
市区町村役場 | 各4通以上 |