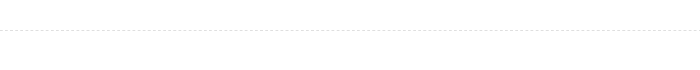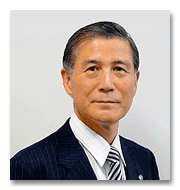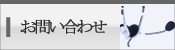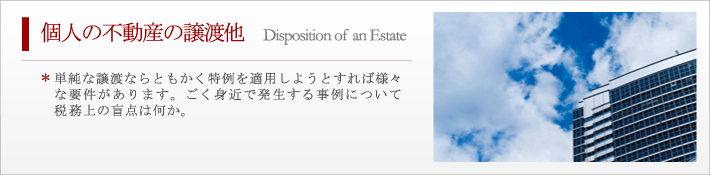個人の不動産取引と税務
a-31. 保証債務の履行による課税所得に対する裁判所の判断 その3
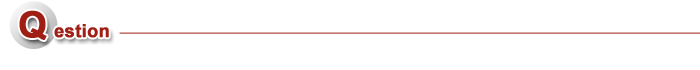
平成16年4月14日さいたま地裁にて納税者が勝訴確定したその内容について
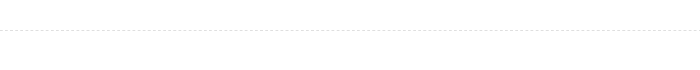
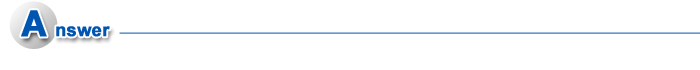
- ① 事案の内容
- (1)この事案は、保証債務履行を余儀なくされたために行われた資産の譲渡ではないという点と、保証付き債務の借換え時点で求償権の行使が不可能であると認められる場合の適用の可否が争われたものです。
- (2)原告はA社の代表者で、土地を担保に連帯保証をしていましたが、業績が回復しないので、会社が通常業務を続けたまま土地を任意売却してA社の借入金を代位弁済しました。
- ② 課税庁の主張
- (1)主たる債務者が債務返済続行中にもかかわらず、原告(保証人)が当該債務を完済し、債権放棄通知書を同債務者に送付していること。
- (2)本案件につき債務借り換え時、原告(保証人)は主たる債務者に資力がなく求償権が行使不能となることを認識していたこと。
- (3)弁済期が到来せず、金融機関からの催告等もないこと。
- (4)本件各土地の譲渡は、本件各債務の弁済期到来前になされているが、融資銀行が、原告に対し、主債務の弁済期限到来前に保証債務の履行を請求した事実はない。
- (5)弁済期限到来前には、連帯保証人も保証債務の履行を強制されることはなく、保証債務の履行のために資産の譲渡を余儀なくされるという事態は想定し得ない。
- (6)特例の「求償権の全部又は一部の行使ができなくなった」という要件は、保証人が自らの努力により、主債務者に対して、求償権を行使しても回収ができなかった場合をいうのであり、保証人が自ら取得した求償権を放棄したり、求償債務を免除したりすることは、単なる所得の処分であって、保証の要件に当たらない。
- ③ 裁判所の見解
- (1)保証人である原告が期限前に代位弁済したのは主債務者であるA社と保証人である原告がともに期限の利益を放棄した結果とみて差支えない。
- (2)保証人は主債務の弁済期の前後を問わず弁済でき、弁済したときに求償権は発生する。債務者は期限の利益を原則として放棄することができる。
- (3)借換え時に保証人は、保証債務を自由に免れることができるものではなく、保証人は従属的な地位に置かれているのが通常であるから、借換え時において、保証人が主債務者に資力がなく、主債務者に対する求償権の行使が不可能であると認識していた場合であっても、旧契約締結時において、保証人が、求償権の行使も可能であると認識していた場合については、所得税法64条2項の適用はあると解するのが相当である。
- ④ 裁判所の判断
- (1)さいたま地裁は、「所得税法64条2項の法意は、保証人が主債務者のために財産を譲渡して弁済し、かつ求償権行使が不能となったときは、資産の譲渡代金の回収不能が生じた場合と同様、結論的にその分はキャピタルゲインたる収入がなかったものと扱うという趣旨であると解される。」としている。
- (2)その上で、所得税法第64条2項に定める保証債務の特例の適用を受けるためには、下記要件が揃えば、これで足りるものであって、それ以上に債権者の請求があったことや主債務者の期限到来が要求されているとは解し得ないという判断をしています。
1.債権者に対して債務者の債務を保証したこと
2.上記1.の保証債務を履行するための資産譲渡であること
3.上記1.の保証債務を履行したこと
4.上記3.の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができなくなったこと。 - ⑤ 国税庁はこの判決については上訴せず、納税者の勝訴が確定しています。