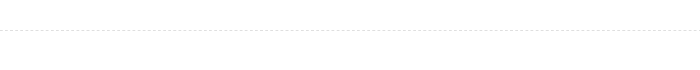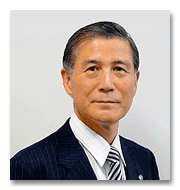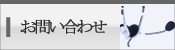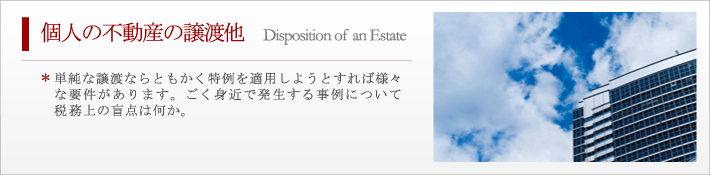個人の不動産取引と税務
a-29. 保証債務の履行による課税所得に対する裁判所の判断 その1
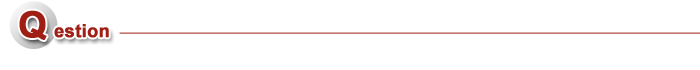
会社の債務について役員が個人保証を行い、不動産を処分して履行した場合の譲渡所得の課税について、過去の判例はどうなっていますか?
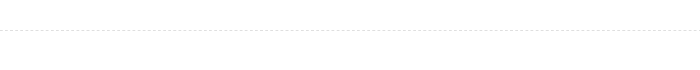
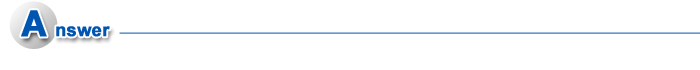
- ① 名古屋高裁昭和57年3月24日の判決より保証契約時における主債務者の資力等の状況把握にも注意
- (1)保証契約時にすでに主債務者が資力を有せず、求償権の行使が不可能であることを知りながら、あえて保証債務の負担を行った場合には、最初から主債務者に対する求償権を前提としないのであり、むしろ主債務者に対して利益供与若しくは贈与した場合と実質的に同視できるとして、譲渡所得の課税対象になります。
- (2)所法64-2は、保証債務を履行するために余儀なくされる不本意な資産の譲渡について課税上の救済を図ろうとする趣旨であり、この場合は最初から求償権の行使が不可能な状態で保証関係に入ったものであり、最初から求償することを予定していないものでありこの特例の適用はありません。
- ② 最高裁昭和61年10月21日判決では事業再建の可能性ありと判断された
- 事実によれば、本件求償権の放棄により法律的には原告XはA社に対し本件求償権を行使できなくなったことは明らかであるが、その場合でも主たる債務者A社に右事業再建の見通しがないこと等の事情がなければ、所得税法64条2項の適用はない。即ち、債権者の求償権放棄の意思表示のみで、その可否を判断すべきではない。
- ③ 平成4年12月1日大阪地裁の判決の内容
- (1)裁判官は「保証債務を履行するため資産の譲渡があったとの要件を充足するためには、資産の譲渡が保証債務の履行を余儀なくされたために行われたものであることを要すると解すべきであり…」として課税庁側の主張を全面的に認めた。
- (2)但し、所法64-2の規定を受けるためには、譲渡代金の全部又は一部が保証債務の履行に充てられており、求償権の全部又は一部が行使できなくなり、損失の金額が事業所得等の必要経費に算入されないことが要件となっています。
- ④ 東京地裁平成7年6月2日判決では利益供与とされた
- 「納税者は、債務者である訴外会社が債務超過の状態にあり、借入金の返済能力がないことを知りながらあえて保証人となったものであって、実質的には債務の引受あるいは、無償の利益供与とみるべきであるから、納税者の本件不動産の譲渡につき所得税法64条2項の適用はない。」
- ⑤ 福島地裁平成8年7月8日判決では利益供与とされた
- 納税者は自分の子供に収入が見込めないこと、したがって、子供に債務の弁済能力がなかったことを十分に認識していたにもかかわらず、あえて、子供のために債務を保証したのであるから、納税者の本件土地譲渡は、所得税法64条2項の適用はない。